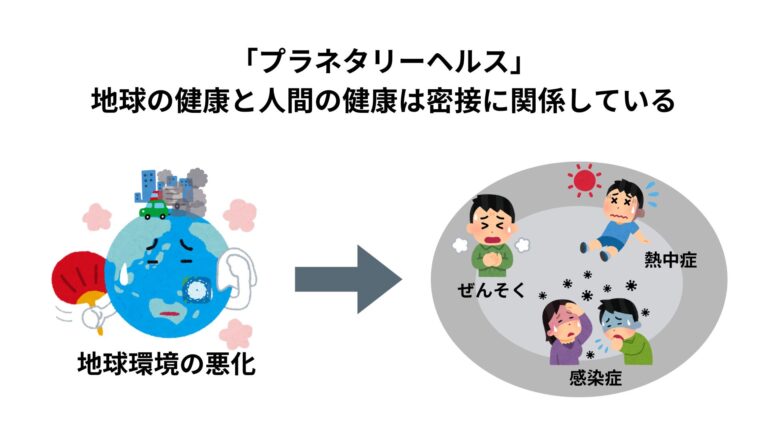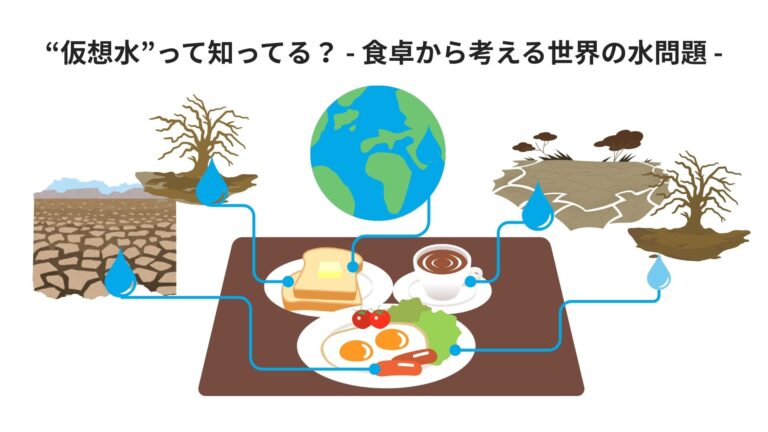本日は、昆虫「ミールワーム」を使用した水産飼料を生産している、株式会社Booon 共同創業者・CEO橋爪海さんに事業内容や会社設立のきっかけをお聞きしました。
事業内容を教えてください
弊社では、ミールワームの昆虫粉を使用した水産飼料を製造しています。
魚の餌を昆虫粉にすることで、現在水産領域で不足している魚粉に代わる新しい動物性プロテインを供給することができます。
基本的に、水産業界では魚の餌に魚粉を使用しています。しかし、近年魚粉の価格が高騰し、20年間で3〜4倍にも増加しました。
そのため、弊社では魚粉に変わる水産飼料をどう確保するかを考え、昆虫粉で代替するという方法を試みることにしたんです。
会社で力を入れている事業を教えてください
現在、力を入れている事業は2軸あります。
1.ミールワームをいかに飼料にするか
集めてきた鶏糞やふすま(小麦製粉時に出るぬか)などの飼料を、ミールワームの餌として最適に加工します。
食品残渣からミールワームに変換するところを、いかに効率的にできるかというところに注力しています。
できたミールワームを加工するプロセスは、既存の魚粉を加工するプラントで粉末化まで可能です。
2.ミールワームを餌にした魚をいかに育てるか
できたミールワームの粉末を、魚の飼料にします。
いかに効率的に魚に吸収できるような資源として活用していくかという部分に注力しています。
なぜ昆虫なのでしょうか?

水産飼料の原料として、最適だと考えているからです。
魚は、鳥や牛、豚と違い消化できる飼料が動物性に限られています。
動物性プロテインを生み出せる方法として、水素細菌を用いた精密発酵など、さまざまな方法が発見されているものの、どうしてもコスト面や、本当に美味しく食べられるのかという問題もあり、これまでスムーズに採用されませんでした。
そのなかで昆虫類は、魚粉とほぼ同じ栄養素で有用に使えるということで、三井物産戦略研究所 2017年のレポートでも高い評価を得ていました。しかし、コストが魚粉の2倍ほどかかるという記載もありました。
ただ、実際にコスト構造を割ってみると、温度管理のための熱源コストが半分ほどを占めていることが分かったんです。
実際2017年から、会社立ち上げに至った2022年までに魚粉の価格は1.5倍ほど高くなっていたので、魚粉と昆虫粉のコスト差は少しずつ縮まってきています。
さらに熱源コストをクリアすれば、魚粉よりも低コストで作れるのではないかと考えました。
昆虫粉を飼料とするメリットはありますか?

昆虫粉のメリットとされているのが、昆虫由来の機能性の部分です。
免疫力向上の効果があるとされており、血流が促進され、魚の血あいが綺麗になり、発色の良い魚が育ちます。
さらに通常の飼料(魚粉ベース)で飼育した魚よりも鮮度が長く保てることも期待されており、輸出に最適と考えています。
また、自然界で、川魚は虫を食べて育っています。そのため、昆虫粉を飼料とした魚の方が、より自然な美味しい魚の味に近づくのではという考え方もできるでしょう。
魚粉と昆虫粉では味は変わりますか?
味は変わらない、もしくはより美味しくなると言われています。
実際に試食会を行ったのですが、昆虫粉を飼料としたサーモンは、通常の飼料で飼育したサーモンよりも脂のりが良いという評価をいただきました。
味自体も、通常のサーモンと遜色なく、美味しく食べていただけました。
「ミールワーム」について教えてください
ミールワームは、主にゴミムシダマシ科の甲虫であるチャイロコメノゴミムシダマシ(Tenebrio molitor)の幼虫をペットの飼料として利用する際の呼称です。爬虫類やカナヘビ、ハリネズミや鳥類の生餌としても普及しています。
ホームセンターでは15g 200〜300円ほどで売られており、釣り餌として使う方もいらっしゃいます。
成虫は小さいカブトムシのような姿で、羽は生えているものの飛べず、雑木林で朽木を食べています。飛んで逃げていくリスクがないので、比較的飼いやすい昆虫とされています。
我々は、このミールワームという昆虫を、焼却処分しているような食品残渣を有効に活用する一つのツールにできないかと考えました。
現在昆虫粉は飼料としてどの程度使われているのでしょうか

いきなりすべての飼料を昆虫粉に変えるのは、飼育方法にも影響が出てくるので、リスクも高いでしょう。
また、全量を昆虫粉にすると、これまでの魚粉と遜色なく魚に食べてもらえるか難しいところです。
実際に昆虫粉の飼料を使ってくださっている企業さんは、5〜15%を昆虫粉に変えています。そのくらいの量であれば、まったく問題なく摂取してもらえます。
魚粉以外のタンパク質も幅広く摂取しているという意味で、免疫力が上がる効果も期待できます。
人がバランス良い食事を摂ることで体調が良くなるのと同様のことが、魚にも起こっているんです。
会社を立ち上げたきっかけを教えてください
以前は陸上養殖の生産ユニットを作る会社をやっており、それがきっかけでまず水産領域に関心を持ちました。
さらに当時私が所属していた長崎大学には水産学部があって、水産系の知見が得やすかったというのもあります。
現場の養殖業者の方と近い距離で話をしていると、餌の価格が高騰し、魚が作れなくなってきているという話をよく聞きました。
そういった現状を理解しているのは、養殖の現場の方と、行政の方だけでした。かなり大きな課題にも関わらず、この課題を分かっている人はほとんどいない。
この現状をどうにか解決できないかと考えたのが、私が現在の会社を立ち上げたきっかけです。
もともと行っていた魚を作る養殖ポットの製造から、ニーズの高い飼料の製造へと、事業が自然に動いていったという感じです。
そもそもどうして水産業界に関心を持ったのでしょう?
長崎に引っ越して、最初に居酒屋で食べた刺身の盛り合わせの魚がすごくおいしくて…!
その時はブリとタイをいただいたんですが、クエのしゃぶしゃぶもとても美味しいんです。
コース料理は飲み放題付きで3,500〜4,000円で食べられます。
当時私は学生でしたが、とても東京では食べられないような魚を身近に食べられたのは、とても良い思い出です。
驚いたのは、長崎の居酒屋で感銘を受けた魚は、養殖産だったんです。
もともと出身は福岡で魚自体は好きだったんですが、養殖の魚の美味しさに驚いたのは、この時がはじめてです。
養殖産の魚の美味しさがずっと記憶に残っていたので、魚粉の価格高騰により
「美味しい魚を作る人たちが、自分たちのプロダクトに自信を持てなくなっている」 という状況がとても悲しいことだなと感じたんです。
美味しい魚を作ろうとしている人の取り組みや養殖産の魚の魅力を、より良い形で発信していけたらなと思っています
生産の仕組み自体をもう少し産業的にし、経済的にも潤うような形で継続的に出来るよう取り組んでいけたら良いですね。
今後の展望を教えてください

短期的には2026年から2027年にかけて、1千トンくらいの規模で飼料の製造プラントを立ち上げる予定です。
製造プロセスを一旦確立してしまえば、養殖業の需要が高まっているアジア圏に出していっても良いのかなと思っています。
今後は、なるべく最適な生産地で飼料原料を供給できる環境を見つけていきたいです。
食も一種の貴重な資源です。アジア圏ではこれだけ養殖の需要が強まっていますので、魚粉不足である日本の課題を解決するためにも、地域ごとの地産地消ができるよう社会実装していけたらと思っています。
さらに長期的な目線で見ると、人が十分満たされた食生活を行えるような資源供給を目指しています。
都市に人口が集まり農村部が衰退していくことで、食自体がその人口動態にあった供給に変わってきているなと感じています。
地域で食材を育てられるような仕組みが確立されていなければ、やがて生活圏が限定されてきた時に、人がその食を得る手段が減ってしまうのではないでしょうか。
その中で、コストがかかるという理由で衰退していくのが水産業なのではないかと危惧しています。我々は水産業の衰退を防ぐためにも、都市型でも成り立つような水産業の生産モデルを確立していきたいと考えています。
やがて宇宙計画で人類が月や火星に移住したとき、現地でタンパク質の供給が求められた際に我々の作った昆虫粉をもとに月や火星でも魚が育てられるようになったら理想的だと思います。
・・・少し壮大な話にはなりましたが、何にせよ、将来の人類に感謝されるような取り組みを行っていきたいと思っています。
(取材日:2024/4/30、6/5)